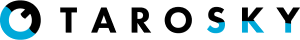デスクトップLinuxのすすめ

久しぶりの投稿になります。インフラ担当のHARAIです。私は仕事でもプライベートでも、パソコンのOSとしてLinuxを使っています。web系の開発者の間ではmacOSが人気ですが、私はここ10年以上ずっとデスクトップLinuxユーザです。その理由について書いてみたいと思います。
開発もLinuxでしたい
Linuxサーバで動くソフトウェア開発をしていると、覚えることがたくさんあります。作業用PCのOSのことまでさらに覚えたくありません。もし開発もデスクトップLinuxで行うことができれば、WindowsやmacOSのことは気にせずLinuxだけに集中できます。
webエンジニアがmacOSを使う理由のひとつに「macOSはUNIXベースなのでLinuxとコマンド体系が同じ」というのがよく挙げられます。ところが、macOSはBSD系でLinuxとは結構な違いがあります。grepのようなよく使うコマンドもオプション体系が異なっており、Linux向けに書いたbashスクリプトがmacOSでは動かないことも多いようです。どちらもUNIXだといっても、結局は2つの世界を覚えなければいけないわけです。
一方デスクトップLinuxはサーバで動いているLinuxと同じですから、そのような問題は起こりません。あるとすれば、ディストリビューションによってディレクトリ構造が違うとか、コマンドのバージョンが違うとかその程度です。限られた脳のリソースを効率よく利用する意味で、デスクトップLinuxで開発することは非常に理にかなっています。
十分安定している
今のデスクトップLinuxは、昔よりもはるかに安定しています。
私が初めてデスクトップLinuxをインストールしたのは1998年頃でした。雑誌の付録CD-ROMからTurbolinuxをインストールしましたが、当時のデスクトップLinuxはひどいものでした。音にノイズが混じる、色数や解像度が上がらない、日本語がきちんと扱えない。とても実作業で使える代物ではありませんでした。Ask Ubuntuのような便利なサイトがなかったのも、問題の解決が困難だった一因だと思います。
ところが2000年代後半、Ubuntuが登場したころから状況が一変。導入のハードルが下がり、特殊なデバイスを使わない限り普通に動くOSになりました。問題が起こってもAsk Ubuntuで調べればたいてい解決します。
ネイティブアプリに代わってウェブアプリが主流になったのも、デスクトップLinuxの選択を後押ししました。ブラウザがOSの違いを吸収してくれるので、ソフトウェア開発の仕事をしている限りアプリケーションが動かず困ることはまずありません。
ほかにも利点がある
ほかにもデスクトップLinuxを使うメリットはあります。
- 問題が起こっても、Ask Ubuntuのような質問サイトからコマンドをコピペで実行するだけで解決することが多い
- ウィンドウマネージャのような普通OSに統合されてしまうような機能がデスクトップLinuxでは分離されており、複数の選択肢がある
- マルウェアの標的になりにくい
- 低スペックのPCでも動く
- WindowsエミュレータのWineを使うと、2000年頃流行った懐かしのWindowsゲームが現在のWindowsマシンよりもきちんと動く
ただ、これらは大きなメリットではありません。やはり、サーバと同じOSが使えるというのが最大のメリットです。
なぜデスクトップLinuxは使われないのか
web系開発者の多くはデスクトップLinuxを使わずにmacOSを好みます。なぜでしょうか?
これは何年も疑問に思っていることです。
一番真っ当な答えとしては「会社がmacOSの使用を前提としているのでデスクトップLinuxは使いにくい」というものがあるでしょう。タロスカイも、多くの部門ではmacOSが標準となっています。でも、2000年代初頭、Windowsに対するMac OS Xがまさに似たような境遇でした。Macだと動かないソフトがある、Microsoft Officeのレイアウトが崩れる。そんな状況でも開発者が「それでもMacを使いたいんだ!」とムーブメントを作ってきて今のmacOSの普及があると思うのですが。
「デスクトップLinuxに移行したいんだ!」となぜ今の開発者は叫ばないのか?
何年か前、同じ話をとあるSNSに書き込んだら「みんな年を取ったんだ」とコメントがありました。確かに自分たちと同じ世代(アラフォー)からムーブメントが生まれないのは年齢的なものかもしれませんが、若い奴らは何をやっているんだ。
そういえば、今度ついに両親のPCにもLinuxを入れることになりました。スペック自体は何ら問題ないマシンなのですが、Windows 11が対応しておらず、Windows 10は今年秋にサポート終了するので。